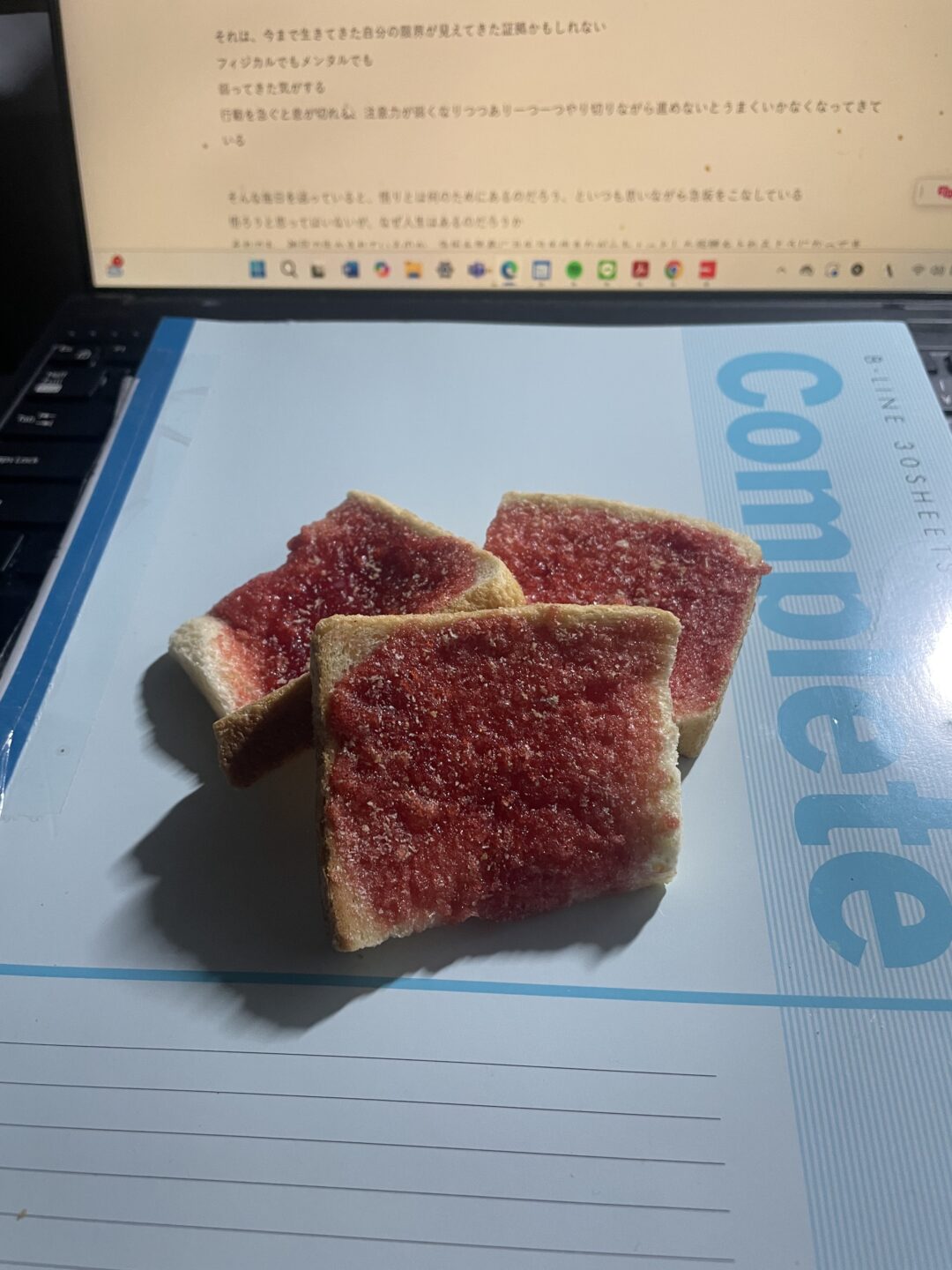朝、7時過ぎに出かけて、物件を貸し出す作業、玄関ドアや掃き出し窓の清掃である 慣れない仕事 それを今日も始める 8時半過ぎから開始するが、11時半ころには嫌になって帰る準備を始める 寒いので、暖房器具を持参したり、食器を用意したり休めるようにすればいいのかも知れないが、ごみごみしたところでお昼を過ごす気もなく、それと一日中格闘する気力もない そこで毎日、帰路はお昼を頬張りながら歩いている ご心配なく、住宅地の閑散とした道だ 手製のお握りと焼いたフランスパン、そしてトマトや野菜を囓る
そして電車に乗るのだが、体が冷えて寒くて仕方がない 凍え死にそうではないが、体は芯から冷えていて気持ちのいいものではない
途中用を足したりして帰宅するが、歩数は1万5千歩前後から2万歩くらいまで 帰宅すると、何しろヒーターで体を温めるのだが、暖まらないのだ 食べ物を補給したり、温かい飲み物はたくさん摂るが・・ そのうち眠くなって机のところでうたた寝する 1時間くらいすると、どこかに頭をぶって目が覚める が、頭はボーッとしていて、気力が失せている
こんなこと、こんな毎日が人生にとって何になるのだ・・、ボーッと現世に戻りつつあるといつもの悪魔のささやきが覚醒と睡眠が混ざった冴えない気分のなかをよぎる
さてさて、そんな毎日を送っていたら、図書館の本を返す期限が明日となった
そう、神戸開港の1986年から1918年頃まで、50年の神戸の物語 ”「神戸外国人居留地」ジャパン・クロニクル紙が記念特別号として発行したジュビリーナンバーをほぼ読み切った
ジュビリーとは、何だろうか
「ジュビリー (英: Jubilee)は、『レビ記』の第25章で ヨベルの年 として記され、 ユダヤ教 で50年に1度の周期で祝賀が行われることに基づく、25または50年に1度の周期で行われる記念日・祝祭または祝年を意味する。 結婚25年に祝われる シルバー・ジュビリー (銀婚式)、50年の ゴールデン・ジュビリー (金婚式)もこれに由来する。」((https://www.bing.com/search?q=ジュビリーとは&qs=LT&pq=ジュビリー&sk=HS1SS1LT1CT1MT2&sc=12-5&cvid=95E4C22AA62041069BA1AA0B9955389D&FORM=QBRE&sp=7&lq=0 参照 2025年2月11日))
まあ、50周年記念号である
このジャパン・クロニクル紙は、1986年創刊ヒョーゴ・ニュース紙を併合しながら50年を迎えたから、確かにゴールデンジュビリーなのだろう 素晴らしい
さて、次に行こう
この本を読み進めると、翻訳本であるとともに古い時代の貨幣価値などが出てきて、私の理解ができているとは決して思わないが、とても興味深いものであったし、途中は冗長に感じたところも多々あった
最初は、この本の立ち位置がよくわからなかったのだが、最後の頃はみえてきた
ジャパンクロニクルにロバート・ヤングという熱心な経営者兼編集者がいて、その人が長年の新聞発行記録を元にしたり、自身が体験したり見聞きしたりした事実や考えを述べたものであることがわかった
印象に残ったところは、随所にあるが
私は、神戸の今の発展と外国人居留との関連を知りたいと思って読んできたのだそれに加え、江戸末期からの王政復古の混乱と明治政府の政策について、教科書に書かれていない事実が書いてあれば、楽しいだろうと思ったからだ それも、外国人の手で書いてあると違う解釈もできるであろう
次に、知ったのは居留地と租界の違いである
その前に、神戸の外国人居留地はいつまで続いたのであろうか
今はもうないことは、なんとなく理解できるし、神戸の街を歩いていても旧居留地という呼び名が定着している
どのくらい存在し、何のためにあったのだろうか
江戸幕府末期、弱り切っていた幕府は、不平等条約を結んでいた 一番が桜田門外の変になった1858年にアメリカ等と結んだ通商条約で
① 外国に領事裁判権を認め、外国人犯罪に日本の法律や裁判が適用されないこと(治外法権)
② 日本に関税自主権(輸入品にかかる関税を自由にきめる権限)がなく、外国との協定税率にしばられていること
③無条件かつ片務的な最恵国待遇条款の承認
である
その中に、1886年の神戸の開港も入っている
1886年9月、造成された土地を、新政府の侍たち(役人)により希望商人たちに競売で売る作業が始まった それは海岸通りと今でいう神戸大丸付近から少し東側の細長い土地であり、旧オリエンタルホテルもその中に入っている
競売ではあるが、要するに永代借地権を売ったことになり、中国香港と同じで返還が求められるものであった 香港は99年だったが、神戸は結果的に1999年7月の改正条約(居留民に言わせると改正条約、日本の教科書では不平等条約)の締結で日本に返還された 約30年の租界地であったことになる 初めて知った
本には関税の点も細々書かれているが、トランプのこともあるのでそうか、昔から欧米の権力者はこれを使うのかと理解はできた トランプは常套手段を使っているだけだ、それも古くさい、100年も昔の植民地帝国時代の手だ ひどいやり方だ、時代錯誤
体が要求していると、私の脳が判断して多量の温かい飲み物とおやつを摂ったせいか、2時間後の今、腹と胸がむかつく
そうだろうな、体は拒否反応もするだろうさ・・
しかし、足から腰は暖かい毛布を巻き付け、足先はフットウオーマー、簡単にいうとコタツに入っている状態だから、最高さ
そして、楽しくブログをしたためている
さて、この本の中で気になったエピソードの一つだけを書き記す
それは、明治初期(M4ーM9)の神田知事(学者知事と言われる)との付き合いを本書の著者が述べている下りだ 神田知事の時代、著者は「日本の農民はまるで奴隷のように使役され、土地を耕作させられていた・・それまでの士族階級に与えられていた特権・・この名誉ある特権を大衆に拡げ・・」「神田氏こそ真に近代的都市・・(日本人も住む)雑居地と居留地の道路を綿密に調査した上で、それをお手本にして、今も残る主要道路を建設した」という 日本人の土木技術は、その当時はひどいものだったのだろう
そして、「兵庫の有力な商人たちの目を港の新しい外国貿易に向けさせようと努力したが、非常に保守的で・・そのために経済的発展の主流は完全に神戸に移り住んできた人々の手に移り、居留地は始めに予定されていた兵庫という名前の代わりに神戸という名が冠せられ・・」
移り住んできた人々とは、日本人も少しはいたかも知れないが、大部分は多国籍の人たちと解釈できる(間違えてはいないと思う)
各停でなく、快速が西から来るとまず静かな街兵庫に停止 そして神戸、元町、三宮駅の順に停まる 街の賑わいはこの順に急上昇する 平清盛の力の源泉であった、瀬戸内海から西の唐までの交易の場であった兵庫の津は、県名に残り、いつしか東、東へと中心部が移動してきた街、神戸 そこに、租界が果たした役割は多分、欧米の新しい風を吹き込み、進取に富んだ人たちを海外に送り込み、反対に欧米の優秀な人材を日本に送り込んでくれたところにあるのだろう さて、それが今どのように神戸の街の文化や人々の暮らしに残っているだろう
それは、ここで住む私の時間の長さが教えてくれると思っている
他にもたくさん、この本には、面白いというか、発想の違いに感動するところもあるが、次の機会に さしあたり略する・・
写真 ラスク3種類用意してある イチジクジャム 黒ごま砂糖 ガーリック を思い切り食べた そして紅茶スティックも何本も 食べ過ぎれば、ムカムカするわ!!
実は、私が見聞きして面白いなと思うこと書いてきているので、神戸の人からは外国人居留地の話なんてよく知っているよ ジュビリーナンバーもゆうめいな話じゃん ということかも知れないが、そこはご容赦願いたい
私は面白いと心を動かされる、その刻が好きだ